|
ゲームの分類に対戦型と協力型というのがあります。
尤も、多くは前者に含まれます。
ゲームとはいわば、勝者を決める手段にルールを定めたものだからです。
・・完全に何かの受け売りみたいですが、ともかく。
ゲームなるものは好きだが勝負事を苦手とする者(=ヌルゲーマー)は、協力型ゲームと銘打たれると俄然ソソられてしまうのです。
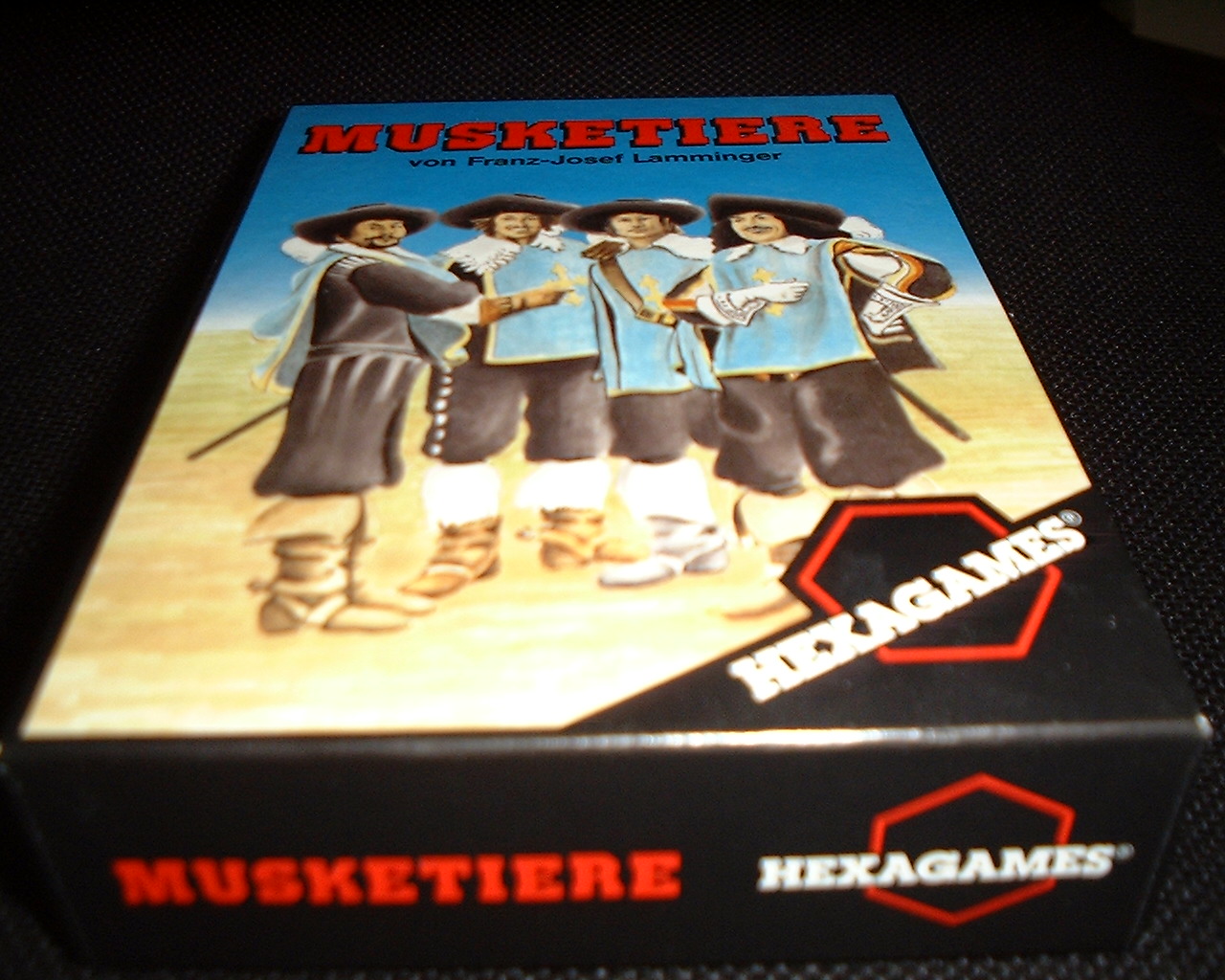
ラテンの血を感じる四人組
さて、この『MUSKETIERE』ですが。
・・あー、
大雑把に云えば、トランプの『戦争』(だったか?)みたいなもんです。
全員が配札から1枚ずつ選び、せーので出して数字の大小で勝敗を決める、という。
ただコレだけだと何でもないので、ここに件の協力の要素が組み込まれています。
すなわち、無作為に「目標値」が設定されるのです(衛兵カードの山から1枚公開する)。
そして、「全員が出した札の数字の合計」がソレ以上なら、最も大きい数字を出した者が勝者となり、ソレを下回れば、最も小さい数字を出した者が敗者となります。
また、得点手段にもひと工夫。
各ラウンドの始めに配札から3枚選んで自分の前に伏せます。それらに記された数字がそのラウンドの最後に得点になるのです。つまり高得点を狙うなら強いカードを諦めねばならないという仕組み。全然違うハズなんですがMagicのアンティを連想します(何でも結びつける病)。
で、前述の勝負に勝つたび、どれか1枚に宝石チットを乗せ、負けるたび牢獄チットを乗せます。
誰か1人が宝石を3つ独占するか、全員手札が尽きればラウンド終了。これを繰り返します。

剣の数はタイブレイクに用います
(例1)
枢機卿の衛兵=7
プレイヤーA=5
プレイヤーB=6
プレイヤーC=2
銃士隊の勝ち。Bが宝石を得ます。

(例2)
枢機卿の衛兵=15
プレイヤーA=0
プレイヤーB=1
プレイヤーC=9
衛兵の勝ち。Aは牢獄を受け取らねばなりません。
単なる読み合いじゃねーの?という話もありますが、自分の勝利には他者の出す札が不可欠な局面が多いので、とても協力し合ってるっぽい印象。殺伐としたゲームが多い中、いいもんです。勝者を決めるというよりMVPを選出するようなもの。
翻ってダメなところも。
ゲームは100点先取なのですが、宝石は乗っているカードの得点を2倍に、牢獄は0倍にします(何も乗ってなければ…そう、1倍です)。
このため、一度オール宝石(中間小説誌ニ非ズ)で得点したプレイヤーにはなかなか追いつけません(一気に50点近く稼ぐのも珍しくなかったりする)。
何よりカードゲームの業とゆうか、配札によってはどーやっても勝てんだろ的な状況もありえます。
なので、まぁ単純な改善案としては、トップとドベで配札のトレードを義務づける、とかしてもいいかと思います。お好みで。
見た目にどうにもアブストラクトなカードゲームですが、不思議と三銃士な感じがします。ホント。
“宝石奪還の命を受けた銃士隊の面々。立ち塞がる枢機卿の衛兵を華麗な連携で薙ぎ倒す。
「流石だな!ダル●ニアン」
「いや、君達のおかげさ…」
それも束の間、新手の屈強な兵が。不意を衝かれた一行。
「ぐぅ・・何て使い手だ」
「うあぁぁっ!?」
「ァ、アラ●スーッ」
・・そして地下の牢獄に幽閉された彼女は(以下略)”
もちろん三銃士読んだことないですけど。はい。
仮邦題:『マスカラス一家の夢冒険』 2006/11/07
| 






